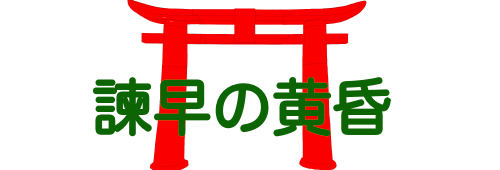- 唐比村愛津村御境目論所内濟覚書
- 御境目事蹟 諫早図書館蔵資料番号No20062
- 諫早 御蔵入北三丁分村 御私領南三丁分村小𢈘倉村 野方山境塚築立證文 諫早図書館資料番号No20039
- 御代参并警固(御代参并警固) 諫早図書館資料番号No20148
- 諸御礼一通(御代参并警固) 諫早図書館資料番号No20148
- 火事場固(諸御礼一通) 諫早図書館資料番号No20148
- 郡方條目(写) 諫早図書館資料番号No20136
- 恒例帳 正徳弐壬辰年 諫早図書館資料番号No20134
- 御内御控 文化十二年 諫早図書館資料No20070
- 年中行事 諫早図書館資料No 20279
- 二十一ヶ条管見 歳暮年始其外御旧例聞書 諫早図書館資料No20277
唐比村愛津村御境目論所内濟覚書
安永八年(1779年)に締結された島原藩愛津村と佐賀藩諫早領唐比村の国境線問題の覚書
当該覚書は佐賀藩側が作成したもので、印形がない写のものです。
増補版森山町郷土史に付随している古文書と内容文章(正)が同じですので、当該写はその正式版から書き写されたものと思います。
諫早日記には唐比村と愛津村の領境問題についての事の顛末が書かれてあり、この覚だけでは分かりにくい部分も、分かりやすいのでは無いかと思います。諫早史談への投稿を参照下さい。
御境目事蹟 諫早図書館蔵資料番号No20062
佐賀藩諫早領と周辺国との御境目に関する記録を纏めたものです。御境を具体的にどこにあるか説明していて、境塚がどの形状で何基あるか等具体的に記述されています。また、境で起きた問題(論所)に関する経緯や御境関係の事件も記載されています。1700年初頭あたりの記録になります(慶應元年(1865年)。再補となっていて、幕末まで諫早家の中でも利用されていたことを示しています。残念な事に、土地の名前は出てきていますが、その土地名がどこを指しているのか不明です。一部、現在の名前と似た土地名もあり、面白いと思います。
当翻刻は諫早史談会で報告がありましたが、その翻刻と自分が以前から行っていた翻刻のいいとこ取りをしています。只、正確でない部分もありますので、もし翻刻され、ここは違うといった箇所がありましたらご連絡ください。
諫早 御蔵入北三丁分村 御私領南三丁分村小𢈘倉村 野方山境塚築立證文 諫早図書館資料番号No20039
本資料は、宝暦十年(1760年)の諫早南三丁分村・小鹿倉村と佐嘉本藩御蔵入地北三丁分村との領境争論の結果、領境としての石塚を築いた時の記録です。南三丁分村と北三丁分村の所在地は、厳密には不明です。『長崎県地名大辞典』には三丁分村は諫早私領江浦村に含まれる旨の記載がありますが、北と南に別れていて北が佐嘉本藩領となっていたことは書かれていません。小鹿倉村は現在の小栗町の一部ですが、明治3年の町村合併時に江浦村と一度合併し、明治22年に小栗村に編入しています。(「鹿」の字ですが、諫早日記には「𢈘」の字を使用していることが多々あります。)
今回の取り交わし証文に至った経緯は諫早日記を調べるとわかると思いますが、以前愛津村と唐比村の論所内濟覚書を読んだ時もそうでしたが、経緯が大変面白く、今回も時間ができた時に読もうと思います。
御代参并警固(御代参并警固) 諫早図書館資料番号No20148
本資料は、「御代参」の方では、佐賀藩の神社での各祭礼やその祭礼に代参として派遣する藩士の格と人数の記載があります。また、「警固」では、長崎奉行や福岡藩主、長崎代官や長崎町年寄、オランダ人が長崎街道を通る際に、どの宿に何人待機するのか等の記載があります。藩外の神社への参詣の手続きも書かれてあり、なかなか面白い物です。
諸御礼一通(御代参并警固) 諫早図書館資料番号No20148
江戸時代は、何かしてもらったことに対して御返礼をするのが一般的でした。旅行のお土産をもらった場合、就職の斡旋をしてもらったり、今でもそのお礼は残っています。
本資料は、その返礼に関する内容ですが、家督相続や養子縁組、元服、氏名変更、加増、帰参等々を受けた場合の返礼の仕方です。実際に返礼はどういう場合に手紙をどういう経路で実施するか、どういう贈り物を返礼品とするかの記載があり、驚くのはほぼ全てが藩主の許可を得て実施されたことに対して、格により藩主までお礼の品を差し上げるのか、またそのルートはどういうふうにするのか等々が書かれています。例えば、諫早領主が「本知」になった際に、藩主には太刀金馬代と縮緬五巻を贈っています。同様の内容が「佐賀藩多久領の研究」でも記載があることから佐賀藩では同様のことが行われていた様です。
火事場固(諸御礼一通) 諫早図書館資料番号No20148
本資料は、出火時の対応や、日頃の各守衛場所の対応、その他雑事に関する対応や処置等の記載があります。また具体的に享保18年に諫早内で付火をした者の処罰内容や、その他具体的な内容の記載もあります。
郡方條目(写) 諫早図書館資料番号No20136
当資料は享保18年(1733)の郡方の法令です。読むと、蔵入地の事、配分地の事が書かれており、諫早領とは関係ない蔵入地のことが書かれていますので、佐嘉本藩発酵の法令集の写しと思われます。但本藩の法令集である鳥の子帳と同じ物ではないですし、この前に書かれている「領中人改様申渡条々(諫早図書館資料No20334)」とも完全一致していませんので、度々本藩から法令が抜き書きされてきたのかもしれません。このこの三資料を突き合わせて比較表を作るのも時代とともにどう変わったのかを見るのも面白いかもしれませんが、またの機会に。。。
恒例帳 正徳弐壬辰年 諫早図書館資料番号No20134
当資料は正徳二年(1712)の諫早家の定期的な事柄の費用や事柄のToDoが書かれています。
題目は、
一 大庄屋勤之事
一 所々番所之事
一 御施餓鬼盆一通之事
一 詣口銭之事
一 銀出方公役勤飯米之事
一 佐嘉諫早御作事方之事
一 輪内掃除并海道一通之事
一 井樋方并橋一通之事
の8項目です。
その他にも定期的に実施する事柄はありそうですが、何故この8項目のみかは不明です。御茶屋の名称、井樋の名称と数(大きさ)等細かな記録があり、これはこれでいい資料です。ご参考ください。
御内御控 文化十二年 諫早図書館資料No20070
当資料は、諫早領主豊前から内附頭人への奥向きを取り仕切る頭人への「掟」としての指示で、最後の方に書かれてありますが、以前よりの決まりを纏めている物の様です。
文化十二年ですが、月日は書かれてありません。最後に豊前印鑑が押されています。
文中、鎖口の運用の仕方(この鎖口が「奥」の事?)、その火の用心、廣式(台所関係)の警備等規定されています。
諫早家では、「掟」がなかなか残っていないので、其中でも珍しい奥向きの掟、詳細を読むと面白いかもしれません。
年中行事 諫早図書館資料No 20279
近世諫早での九月から六月迄の恒例行事に関する記録です。
この書類が何時ごろ描かれたのかは記載がありませんが、文化年間〜天保年間(1804〜1843)頃の年代が見られます。記載の行事は、多くは諫早領内での神社祭礼に関するものです。また相続に関する事、法事に関する事等々書かれています。諫早日記と合わせて研究するのに面白そうです。ご参考まで。
二十一ヶ条管見 歳暮年始其外御旧例聞書 諫早図書館資料No20277
この書類は、二十一ヶ条の御遺訓と年末年始の旧例を纏めた文書の2部構成になっている。二十一ヶ条の遺訓は背景が書かれており、藩の起こりと遺訓を知らずして徳を広めることができるのかということが書かれている様であるが、文体が難しく中々理解が難しい。翻刻してみたが、はっきり言って下名には内容を理解出来なかった。読者の方々には参考になるかどうか分からないが、原本と見比べつつ翻刻の参考としていただきたい。
年末年始の旧例の方は、鍋嶋勝茂時代から続く嘉例の詳細が書かれている。年末年始の行事、その他の盆や毎月の行事等が書かれている。面白いのが歳暮に行われる「ブリの包丁」と呼ばれる恒例行事、勝茂公が朝鮮出兵した時の出来事により始まったと書かれている。その他、色々な行事が謂れと共に記載されており、分析すると面白い研究になるかもしれない。
毎度の事だが、当翻刻は、あくまでもご参考まで。もし翻刻内容のご指摘があれば、メールで頂ければ嬉しい限りです。