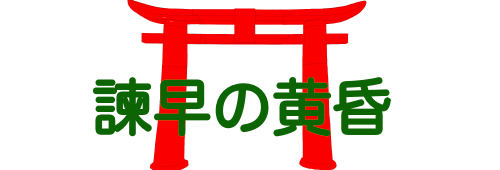諫早神社甕製鳥居 諫早史談53号
諫早神社には大正八年寄進の甕製の鳥居が存在しました。この製造記録は無いものの、諫早亀山焼きの内田伊左衛門が作成し、寄進したものと思われます。甕を焼く技術で作られた鳥居は非常に珍しく、全国でここだけだったと思われます。その為、昭和初期に鳥居の研究が発展しますがそれらの本にも、この鳥居の存在は記録されます。
昭和32年(1957年)7月25日に発生した諫早大水害にて、この鳥居を流出してしまいます。それ以降、人々の記憶から忘れ去られ研究する方もおらぬまま現代に至ります。後世に残すために、研究の一助として諫早史談に寄稿しました。
島原領愛津村と諫早領唐比村の領境問題 諫早史談54号
安永八年(1779年)に起きた島原藩愛津村(現雲仙市愛野町)と佐賀藩諫早領唐比村(現諫早市森山町唐比)との領境問題について、お互いに合意した際の覚書を入手しました。その覚書は最終結論のみでそこに至る経緯がよく分かりませんでしたので、諫早日記から領境問題に関する記事を抜き出し、発生から合意までの経緯を纏めました。諫早日記には佐賀藩の役人の領境問題に関する考え方も記載があり、どういう思いで解決まで導いたのかもわかる事が出来ました。また、同時期に佐賀藩諫早領網場(現長崎市網場町)と御料日見村(長崎市宿町)との間で勃発した領境問題が長崎代官の手に委ねられ、非常に激しい論争になった為、この唐比村と愛津村との問題を早く解決したかったように伺えます。
ガン爪考 諫早史談55号
ガン爪は、近世1700年頃に久留米藩国分村に居住していた笠九郎兵衛(りゅうくろべえ)が発明しました。用途は水田の一番草を除去するための道具ですが、爪が非常に長く柄が短いため、水田の土深く突き刺さり、土を返して草を根から取り除くのに非常に使い勝手が良かったようです。名称を「蟹爪」と書き、「ガンズメ」と呼びました。その後佐賀藩に伝わり、ここで改良が加わり「雁爪」となりましたが、この雁爪が西日本へと広がります。1822年出版の「農具便利論」では「西国ではこのような便利な道具が使われている」との評価でかかれています。
方や、諫早ではこの雁爪は伝わらず、同名で別のものが使用されていきます。
明治、大正、昭和と過ぎ、この雁爪はどう展開していくのか迄、記載しています。
多良見町領境石と郡境石の地伏石の発見 諫早史談56号
諫早市多良見町の井樋ノ尾には長崎市古賀町から続いている長崎往還道が通っています。其地点は近世では佐賀藩諫早領と大村藩との領境でした。領境には通常それぞれの藩側に藩を示す標柱が立っています。現在は、場所を違えて佐賀藩を示す標柱が諫早市指定文化財として残っています。その標柱は諫早領の行政文書である諫早日記には「榜示石」と書かれ、其土台に榜示石を固定するために両側からコの字形の石で挟んでいました。これを地伏石(じふくいし)といいます。
今回、その佐賀藩領境石の地伏石ともう少し諫早側に進んだ箇所にある彼杵郡と高木郡の境を示す榜示石の地伏石をそれぞれ発見しました。
肥前鳥居の分類と定義 諫早史談56号
ずっと以前から鳥居に興味があり、其中でも肥前鳥居と分類されている鳥居について調査研究を実施してきました。「肥前鳥居」と呼ばれる鳥居の分類は、昭和十八年に根岸榮隆が提案したと思われますが、肥前鳥居とはどういうものか明確に書かれていません。色々な方のHPや各教育委員会での記述等には、肥前鳥居の定義がバラバラで統一されていません。実際肥前鳥居を見ると年代ごとに変化しており、また地域によって状態が色々あり、上記で定義されている「肥前鳥居」に当てはめると、肥前鳥居ではない肥前鳥居があったりと、かなり曖昧模糊な「定義」であることが否めません。
そこで、今一度、肥前鳥居とはどういうものか、佐賀、福岡、長崎に存在する肥前鳥居と様々な方の本や論文から再定義を行いました。